元旦に掃除してしまっても必要以上に不安になる必要はありません。正しい対処と捉え方で新年の運気は取り戻せます。
「元旦に掃除なんてしてしまった…。縁起が悪いって聞いたのにどうしよう。」
お正月、気がついたら掃除してしまったあなた。カーペットに落ちたパンくず、子どものおもちゃに残った泥、玄関の砂…。どうしても気になって掃除機を手に取ったその瞬間、ふと頭によぎったのは「年始に掃除をすると“福を掃き出す”って言うよね?」という昔ながらの言い伝えだったのではないでしょうか。
年神様がやってくるとされる元旦。昔からの風習では「掃除・洗濯・火・水の使用」を慎むといわれてきました。しかし、それを知らずに掃除してしまった場合、「バチが当たるのでは」「今年の運気が下がるのでは」と不安になる方も多いようです。実際、「元旦に掃除してしまった」と検索されている数は毎年のように増加傾向。Q&Aサイトでも同様の悩みが頻出しています。
けれど、どうか安心してください。元旦に掃除してしまったからといって、運気や幸福がすべて失われるわけではありません。
そもそも「なぜ元旦の掃除がNGとされているのか?」という背景や、「本当に“福を掃く”ことになるのか?」という部分を、現代の暮らしと照らし合わせながら見直してみることが大切です。
たとえば、小さな子どもがいる家庭やペットを飼っている家では、どうしても清潔を保つ必要があります。年末にゆっくり掃除できず、やむを得ず元旦に掃除したという方も少なくないでしょう。そうした“暮らしの事情”に寄り添わず、「縁起が悪いからダメ」と一刀両断するのは、少し乱暴かもしれません。
さらに、最近では片づけコンサルタントの近藤麻理恵さん(通称こんまり)による『ときめき』の片づけ法が注目されています。「モノに感謝して手放す」「掃除ではなく整える」という考え方は、元旦の片づけにも応用が利きます。こうした視点を取り入れることで、“福を掃く”どころか、むしろ新年の良い運を呼び込む準備にもなるのです。
このブログ記事では、うっかり掃除してしまった人のために「なぜNGと言われるのか」「それは本当に問題なのか?」を丁寧に解き明かしながら、心が軽くなる5つの対処法をご紹介します。風習や迷信に振り回されすぎず、かといって無視するわけでもなく、伝統と今を調和させながら新年を心地よくスタートする方法を、一緒に考えてみませんか?
この記事は以下のような人におすすめ!
- 元旦に掃除してしまい、後から「縁起が悪いかも…」と不安になっている
- 年末に掃除が間に合わず、お正月に家を整えたくなった
- 「元旦に掃除はNG」と親に言われたが、納得できない
- 風習を尊重しつつ、今の暮らしに合った行動を知りたい
- 掃除や片づけを“福を呼ぶ習慣”として活かしたい
目次 CONTENTS
1. 元旦に掃除してしまった…それって本当にNGなの?
元旦の掃除が「運気を下げる」と言われるのは、年神信仰などに基づく民俗的背景があります。
新しい年を迎える元旦。晴れやかな気分とともに、「今年こそ部屋をきれいに保ちたい」と意気込んでいた矢先、ふと気になった汚れを掃除してしまった方も多いかもしれません。そして、掃除を終えてから「元旦の掃除は福を掃き出すって聞いたことあるけど…大丈夫だったかな?」と、不安にかられた経験はないでしょうか。
実際、「元旦に掃除してしまった」と調べている人が後を絶たないことからも、多くの人が同じような疑問や後悔を抱えていることがわかります。では、本当に元旦に掃除することは“縁起が悪い”のでしょうか?ここでは、そのルーツや心理的背景をひも解きながら、現代人が抱える葛藤に寄り添って考えていきます。
1-1. 「福を掃く」とは何か?日本の年始風習に見る由来
日本では古来より、正月には「年神様(としがみさま)」と呼ばれる神様が家々を訪れると信じられてきました。年神様はその年の福や実り、健康をもたらす存在とされ、家の中を整えてお迎えすることが大切と考えられています。
このような年神信仰から派生して、年末の大掃除には“けがれを祓い、神様を迎える準備をする”という意味が込められました。逆に元旦以降に掃除をすると、せっかく訪れた年神様を追い出してしまう、つまり「福を掃いてしまう」という考えが生まれたのです。
さらに、江戸時代には「正月三が日は静かに過ごすもの」とされ、家事や外出も最小限に控えることが礼儀とされていました。こうした風習が「元旦の掃除=NG」という通念につながっているのです。
1-2. 迷信と事実の境界線:科学的・心理的に“本当に悪い”のか?
こうした年始の風習は、地域や時代によって少しずつ異なります。「掃除してはいけない」というルールは、あくまで伝統に基づいた文化的なものであり、科学的に証明された“運気低下の因果関係”は存在しません。
むしろ、掃除によって空間が整うことで、脳や心がリフレッシュされる効果は多くの心理学研究でも明らかになっています。きれいな部屋は集中力や幸福感を高め、無意識レベルで「前向きな思考」を促進することが知られているのです。
つまり、元旦に掃除をしてしまったからといって、不幸が訪れるとは言い切れません。大切なのは「どうして掃除をしたのか」「その行動をどう受け止めるのか」という自分自身の意識なのです。
1-3. 「掃除してしまった」罪悪感はどこから?現代人の葛藤に迫る
「やってしまった…」という罪悪感は、多くの場合、自分自身の価値観ではなく、“人からどう思われるか”という外的な視線に由来します。
たとえば、「おばあちゃんに『元旦に掃除しちゃダメって言われた』」「SNSで縁起が悪いと知って慌てた」など、周囲の声や文化的刷り込みによって後悔が芽生えるケースが多いのです。
しかし、私たちは皆それぞれの生活スタイルを持ち、年末に仕事や育児で掃除できなかった事情もあります。完璧であることを求めすぎず、「できるときに整える」ことを選んだ自分を肯定してあげることが、何より大切なのではないでしょうか。
心理的にも「してしまった行動」よりも「そのあとの考え方や感情の持ち方」が、幸福感や自己評価に強く影響することが多いとされています。たとえば、「掃除しちゃったけど、清々しい気持ちで新年が迎えられたからOK」と捉えられたなら、むしろそれが新たな福を呼ぶきっかけになるはずです。
ポイント
- 元旦の掃除NG説は年神信仰や江戸時代の風習に由来する。
- 科学的には掃除が幸福感や脳の活性化を促すこともある。
- 「やってしまった」より「どう受け止めるか」が鍵となる。
2. 運気が下がると言われる理由とその根拠
元旦掃除が忌避される理由には「年神様」「邪気」「家のけがれ」など、伝統的な象徴が絡んでいます。
「元旦に掃除をすると、福を掃き出してしまう」「年始の掃除は運気を落とす」。こうした言い伝えは一体どこから来たものなのでしょうか?元旦の掃除にまつわるタブーは、迷信という言葉だけでは片づけられない長い歴史と文化的背景を持っています。
ここでは、その成り立ちを深掘りしながら、なぜ「運気が下がる」と考えられるようになったのか、その根拠を3つの視点から明らかにします。
2-1. 年神様と正月行事の関係:「清める」と「留める」の矛盾
正月にお迎えする年神様は、五穀豊穣や家族の健康を司る神として、家の中の「清らかさ」が重視されてきました。そのため、年末には「すす払い」として大掃除が行われ、年神様を迎える準備を整えるのが日本古来の正月行事です。
ところが、年神様を迎えた後に再び掃除をしてしまうと、せっかく訪れてくれた神様を追い払ってしまうことになる――という考えから、「元旦に掃除をするのは縁起が悪い」とされるようになったといわれます。
これは、「掃除=清め」とする視点と、「掃除=追い出す」とする信仰的解釈が同居しているからこそ生じた矛盾でもあります。つまり、文化的には「年末は掃除をして清める」「年始は神様を定着させる」役割が違っていたわけです。
2-2. 風習としての「動かない正月」:動くほど“縁”を逃す?
江戸時代には「正月三が日は静かに過ごす」ことが上流階級の作法とされ、それが庶民にも広まっていきました。そのため、掃除だけでなく、洗濯・料理・水仕事・火の使用など一連の“家事”は極力控えるのが理想とされたのです。
この「動かないお正月」には、実は別の意味も込められていました。“縁を留める”ために動かないという発想です。動くほど、福や縁、家族のつながりまで「動いて離れてしまう」というイメージがあったため、静かに、慎ましく過ごすことが良しとされてきました。
また、昔は冬の水道や火の使用も体への負担が大きく、実際に体を壊す原因にもなっていたことから、「正月は無理をしないように」という生活の知恵でもあったとも言われています。
2-3. 掃除以外にもある!正月NG行動の背景とは
掃除に限らず、お正月には「してはいけない」とされる行動が他にもいくつかあります。たとえば
- 洗濯をしない:「水で福を流してしまうから」
- 針仕事をしない:「目が悪くなる・集中しすぎて神様を無視する」
- 火を使わない:「災いを呼ぶ火の神を刺激しないため」
- 包丁を使わない:「切る行為が縁を断つとされる」
こうした行動はすべて、「縁を保ち、神様を喜ばせる」ための象徴的な意味が込められているのです。
しかし、現代では住環境も働き方も多様化し、「正月に全ての家事をやめる」ことが現実的ではない家庭も増えてきました。よって、こうした風習を「そのまま守るべきか」ではなく「どう取り入れるか」という視点で考えることが、今の暮らしに合った運気との向き合い方だと言えるでしょう。
ポイント
- 元旦掃除NGは「年神様を追い出す」という信仰が背景にある。
- 江戸時代の「動かないお正月」は“福を留める”ための生活文化。
- 火・水・刃物などもNGとされるが、現代では柔軟な受け止め方が必要。
3. うっかり掃除してしまった!現代に合った正しい対処法5選
元旦に掃除してしまっても、落ち込む必要はありません。意識を変える対処法で“縁起直し”が可能です。
「やってしまった…」。大晦日にバタバタしていたり、年明け早々に汚れを見つけて掃除をしてしまった方にとって、「福を掃いたかもしれない」という不安は想像以上に尾を引くものです。
でも、安心してください。元旦に掃除してしまったからといって、すべてが台無しになるわけではありません。むしろ、それをきっかけに空間と気持ちを整えられるなら、新年の運気は自分で好転させることができるのです。
ここでは、「もう掃除しちゃったけど、どうすれば気持ちを立て直せる?」という人のために、現代生活に即した5つの対処法をご紹介します。
3-1. 「お詫び」ではなく「リセット」へ:神棚・玄関の整え方
まず、「掃除してしまった」ことに対して後悔するよりも、神聖な場所に敬意を払ってリセットする行動に変えてみましょう。
たとえば、神棚がある家庭では、手を合わせて「新年を穏やかに過ごせますように」と一言添えるだけでも、気持ちは大きく変わります。神棚がない場合でも、玄関を整えることは“福の入り口”を清める行為として効果的です。
- 靴をきれいに揃える
- ドアノブや表札を拭く
- 正月飾りがあれば位置を整える
こうしたシンプルな動作でも、「整える=受け入れる姿勢」に通じ、新年を肯定的にスタートさせることができます。
3-2. “静かな掃除”へ転換:モップ・アロマ・自然乾燥でバランスを
もし元旦に汚れが気になった場合、音や動作を控えめにする「静かな掃除」に切り替えるのもひとつの工夫です。
- 掃除機よりもモップやフロアワイパーを使用
- 乾拭きや重曹など音を立てない清掃法を選ぶ
- 芳香剤ではなく、アロマやお香で空間を整える
こうした“音を立てずに整える行為”は、年神様を驚かせず、自分自身の心も穏やかに保てる掃除法として、年始に適した方法と言えるでしょう。
3-3. 「盛り塩」や塩風呂で浄化:気持ちと空間を切り替える方法
どうしても「運気が下がった気がする」と不安な方は、昔ながらの“浄化の手段”を活用するのがおすすめです。
- 玄関や部屋の四隅に盛り塩を置く
- 粗塩を湯船に入れて“塩風呂”で心身を整える
- お香や線香で空間のけがれを流す
これらの方法は科学的な根拠は薄いですが、心理的な「気持ちの切り替え」に大きな力を発揮します。行動が心を導くという点で、迷信ではなく「気を整える技術」として受け止めてみてはいかがでしょうか。
3-4. 翌日の「福迎え」行動:神社参拝・飾り直しのすすめ
元旦に掃除してしまったとしても、翌日に「福を再び迎える行動」をとることで、気持ちをリセットできます。
- 初詣に行って新年の誓いを立てる
- 正月飾りを整え直す(軽く拭き、向きを調整)
- 玄関に一輪花や緑を飾る
こうした“迎えなおし”の行動は、「失った」と感じていた運気やご縁を、自ら取り戻す意志の表れになります。年神様も、そんな姿を見てくれているかもしれませんね。
3-5. 家族と共有する「大丈夫ルール」:気にしすぎない心の整え方
最後に大切なのは、「自分だけが気にしているかもしれない」という視点を持つことです。
元旦に掃除をした事実が、他人に責められるほど重大なことかと言えば、決してそうではありません。それよりも、「私は福を招く準備をした」「空間も心も整った」と前向きに捉える姿勢の方が運気を引き寄せるのではないでしょうか。
家族がいる場合は、「福を逃したかも…」と内心で悩むのではなく、「でも気持ちよく過ごせるからOKってことにしよう」と共通ルールを作るのもひとつの方法です。お互いに「それでいいよね」と納得し合うことで、穏やかな気持ちで一年をスタートできます。
ポイント
- 神棚や玄関を整えることで「新たな迎え入れ」が可能。
- 静かな掃除や塩風呂で、心のバランスを整える工夫を。
- 翌日の“福迎え行動”や家族との共通ルールが支えになる。
4. こんまりメソッドに学ぶ「運を逃さない片づけ方」
元旦でも「ときめき」を基準にしたこんまり式片づけなら、心と空間を整え運気を引き寄せられます。
「元旦に掃除してしまったけれど、やっぱり部屋が整うと気分がいい」。そんなあなたにおすすめしたいのが、世界的にも注目されている片づけ法「こんまりメソッド」です。
掃除とは異なり、“片づけ”は空間の意味づけや感情の整理に深く関わる行為。とくに年の初めには、「物を捨てる」のではなく、「感謝して整える」行動が、結果として運気アップにもつながります。
ここでは、うっかり掃除してしまった人でも前向きになれる、“縁起を高める片づけの考え方”をこんまり式視点で解説していきます。
4-1. 「捨てる」ではなく「感謝して手放す」行動が鍵
こんまりメソッドの核となる考え方のひとつが、「ときめくかどうかで残す物を選ぶ」という視点です。これは単なる整理整頓とは違い、持ち物との心の対話を重視するスタイルといえます。
年始のタイミングで物を片づけるとき、「縁起が悪いから掃除してしまった…」という罪悪感からではなく、「今年は気持ちよく過ごすために空間を整えたい」と考えてみてください。
その際、古くなったものや使わないものに対しては、「ありがとう」と声をかけてから手放すことで、自責ではなく感謝をベースにした行動になります。これは「捨てる」という行為をネガティブな印象から救い出し、むしろ“空間と心を開く”きっかけとなるのです。
4-2. 年神様も喜ぶ空間づくり:モノと対話する意味
年神様を迎える正月こそ、「片づけ=神様へのおもてなし」として活用できます。
たとえば、玄関に置かれた靴や傘立て。いつも何気なく置かれているモノたちも、一つひとつの意味を見直してみましょう。
- 「この靴でどんな思い出があったか?」
- 「このカバンは今の自分に必要か?」
- 「この置物はまだ“ときめく”だろうか?」
このようにモノと対話することで、空間が今の自分にふさわしい状態へと整っていきます。そしてそのプロセス自体が、「迎え入れる準備」としての役割を果たしてくれるのです。
年神様にとっても、意味のあるモノで整えられた空間は居心地がよく、運気を長く留めやすくなるとも考えられます。
4-3. 掃除と片づけの違い:「動かすこと」より「整えること」へ
「掃除」と「片づけ」は似ているようで違います。掃除は主に“汚れを落とす”ことですが、片づけは“物の意味を再確認し、位置を決める”作業です。
年神信仰における「掃く行為」がNG視されがちなのに対し、片づけは“動かさずとも整える”ことができる行為です。
- 扉の前にある荷物を「少し寄せる」
- よく使うものの定位置を決める
- 一軍の道具だけをすぐ手に取れる場所に置く
こうした“動かさないけど整える”行為は、年始にぴったりの片づけアプローチです。とくに元旦に動きすぎたくない方には、エネルギーの流れを調整する静かな片づけ法として最適です。
ポイント
- 「ときめき」で選ぶ行為が感謝と縁起の循環を生む。
- モノと向き合うことが、年神様へのおもてなしにつながる。
- 掃除よりも“整える”片づけが元旦にはふさわしい行動。
5. 元旦に掃除してもOKな場合とは?ケース別の判断ポイント
実際には、すべての元旦掃除がNGとは限らず、地域差や家庭事情によって柔軟に判断できます。
「元旦の掃除は縁起が悪い」と言われる一方で、現代の暮らしの中では“掃除せざるを得ない事情”がある人も多いのが現実です。
家族の健康、衛生管理、小さな子どもやペットのいる環境、高層マンション特有の生活音問題…こうした日常に直面したとき、風習だけを優先するのは現実的ではありません。
ここでは、「元旦に掃除をしてもOK」と考えられる、現代的な判断基準を3つの視点でご紹介します。
5-1. 子どもやペットがいる家庭:清潔と縁起のバランスとは
小さな子どもがハイハイをしたり、ペットが室内で過ごしている家庭では、掃除をしないことで健康を損なうリスクがあります。
年末にきちんと掃除ができなかった家庭も少なくなく、元旦に床がベタついていたり、ほこりが舞っていると「清潔さ」よりも「縁起」を優先することに違和感を覚えることもあるでしょう。
この場合、「福を掃く」のではなく「病気を防ぐ」行動だと捉えることが重要です。むしろ、掃除することで家族が健康に過ごせるなら、それは“福を守るための行動”だといえるのではないでしょうか。
また、掃除の範囲を限定したり、静音で行うなど工夫することで、風習とのバランスも保てます。
5-2. 近所迷惑・騒音配慮の視点:「時間帯」と「音」の問題
マンションや集合住宅で暮らす方の中には、「掃除音が迷惑になるのでは」と気を使って元旦を迎える方も少なくありません。
掃除そのものよりも、「音を立てるタイミング」に配慮すれば十分というケースもあります。
たとえば
- 朝8時前や夜間の掃除機は避ける
- 乾拭きやワイパーで静かに対応する
- 掃除ロボットは休止設定にしておく
こうした配慮によって、「福を掃く」のではなく、「福と調和する環境づくり」が可能になります。
また、近隣への気配りができる人こそ、“ご縁を大切にする人”として年神様も微笑んでくれるかもしれません。
5-3. そもそも「三が日」信仰はどこまで続くのか?
実は「三が日を静かに過ごす」という風習は、明確な全国共通ルールではありません。地域によっては、元旦だけは動かないが、2日からは洗濯や炊事を再開してよいとされている場合もあります。
つまり、「三が日はすべて掃除禁止」と思い込んでいるのは、過去の慣習が現在にそのまま持ち込まれただけのことも多いのです。
地域の年中行事に詳しい親世代に聞いてみたり、自分の家庭での“ちょうどよいルール”を見つけることが、心の安定にもつながります。
「これはOK、これはNG」という一律のルールではなく、“暮らしの中で何を大切にしたいか”を軸に判断する柔軟性が求められる時代です。
ポイント
- 衛生面や家族の健康を優先する掃除は“福を守る行動”にもなる。
- 騒音や時間帯に配慮すれば、掃除行為も穏やかな行動に変わる。
- 風習は一律ではないため、自分に合った「安心のルール」が大切。
6. Q&A:よくある質問
6-1. 元旦に掃除したら本当にバチが当たるの?
結論から言えば、「バチが当たる」と断言できる根拠はありません。
「バチが当たる」という表現は民間信仰や風習に由来するもので、科学的・宗教的に因果が証明されているものではないため、気持ちの問題として捉えるのが妥当です。
むしろ、自分の家を清潔に保つことは、健康や安全にとって非常に価値ある行動です。バチを恐れるより、「今日を丁寧に過ごそう」と意識を変えることで、より前向きに新年を迎えられるでしょう。
6-2. 掃除機や洗濯機の音はNG?時間帯で対策できる?
音が気になる場合は、時間帯と掃除方法を工夫するのがベストです。
元旦だからといって機械の使用が絶対NGというわけではありませんが、「午前中は年神様がいらっしゃる」とする地域風習もあります。以下のような配慮が現実的です。
- 掃除機は午後に短時間で済ませる
- フロアワイパーやモップで静音掃除に置き換える
- 洗濯は脱水を省く or 室内干しで音を抑える
つまり、“完全NG”ではなく“調和を意識した使い方”が正解なのです。
6-3. 掃除したあと、どうしても不安が残る時は?
気持ちの上で「運を逃したかも…」という不安が消えないときは、意識を“整える行動”へと切り替えるのがおすすめです。
たとえば
- 神社や氏神様にお参りして新年の誓いを立てる
- お守りを新しくする
- 盛り塩・塩風呂などで自分なりの浄化を行う
これらの行動は、「やってしまった」という感情を“新たな始まり”に変えるスイッチになります。迷信に振り回されるのではなく、「自分で福を呼び込む力がある」と信じることが最も効果的な開運行動です。
6-4. 親から怒られた…どう言い返す?
これは多くの人が経験する悩みかもしれません。世代間で風習に対する価値観が違うため、反発せず、尊重と自己判断を両立する言い方が効果的です。
例
「お母さんの教え、大事にしてるよ。でも今年は赤ちゃんもいるし、清潔優先で整えたの。気持ちはしっかり込めたよ。」
このように伝えることで、親世代の価値観を否定せず、自分の選択にも納得を持たせる会話が可能になります。
6-5. 三が日を過ぎても掃除しない方がいいの?
いいえ、三が日を過ぎれば、掃除や洗濯を再開する家庭がほとんどです。元旦のみを特別視する地域もありますし、2日・3日は「福を整える日」と捉える風習もあるほどです。
風習の正解は一律ではありません。“気持ちよく新年を迎える”という本質を守っていれば、やり方は柔軟で構わないという考え方を持つと心が楽になります。
ポイント
- 「バチが当たる」は迷信的側面が強く、現代では気にしすぎないのが大切。
- 音やタイミングを調整すれば、元旦でも掃除は可能。
- 不安な時は“整える行動”で気持ちを切り替えるのが効果的。
7. まとめ:気にしすぎず、新年を清々しく迎えるために
元旦の掃除は“悪いこと”ではなく、どう受け止め、どう行動するかが大切です。
「元旦に掃除してしまった…」
そんな不安を抱えるあなたに伝えたいのは、それだけで“運気が下がる”ことはないという事実です。
本記事では、掃除がNGとされる文化的背景や、現代における柔軟な捉え方、そして心を軽くするための実践的な対処法をお届けしました。
ポイントは次の3点に集約されます。
1. 「元旦掃除NG」は信仰と風習に基づくもので、科学的な根拠はない
年神様を迎えるという伝統的な価値観から、「掃除をすると福が逃げる」という考えが生まれました。しかし、これは民俗的背景によるもので、実際に不運が起こるとは限りません。
むしろ、清潔を保つ行為や空間を整える片づけは、現代人にとって必要な“生活の基盤”でもあります。
2. 対処法の実践で「縁起直し」は可能。福は自分で呼び込める
神棚や玄関を整える、盛り塩や塩風呂で浄化する、静かな掃除に切り替える…。こうした“意識的な行動”が不安を希望に変える力を持っています。
さらに、「ときめく」ものを選び整えるこんまりメソッドのように、自分の心と対話しながら空間を整える行為は、“福を呼ぶ準備”そのものになるといえるでしょう。
3. 暮らしに合わせた“安心ルール”を家族や自分と共有しよう
正月の過ごし方に「これが絶対正解」というものはありません。大切なのは、自分の暮らしに合った考え方と行動を選ぶこと。たとえ元旦に掃除をしてしまったとしても、丁寧に過ごそうとする気持ちがあれば、それは“けがれ”ではなく“整え”です。
親世代の価値観を尊重しつつ、自分の判断を肯定し、「大丈夫」と言い合える空間づくりこそが、令和時代の新しい正月のあり方ではないでしょうか。
最後に:気に病むより「整える」
運気とは、不安に支配されるほど遠ざかっていきます。
「整える」「感謝する」「迎え入れる」。この3つの視点があれば、たとえ元旦に掃除してしまっても、自分で福を招くことは可能です。
新しい一年、誰よりも早く「整った空間」と「自分を肯定できる心」を手に入れたあなたに、きっとすばらしい福が訪れるはずです。
ポイント
- 元旦掃除を過度に恐れる必要はなく、自分なりの整え方で十分。
- 行動次第で運気の切り替えは可能。気持ちを切り替える工夫が鍵。
- 大切なのは、「どう過ごすか」を自分と家族で決めていく姿勢。










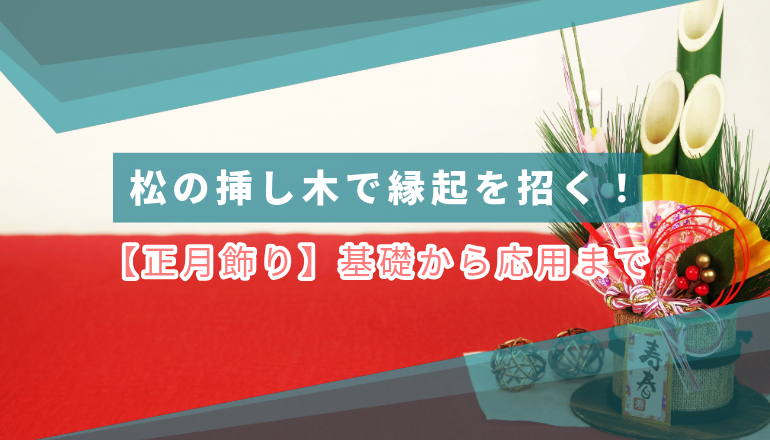

コメント